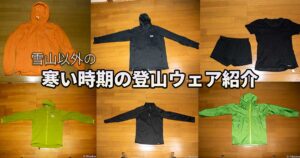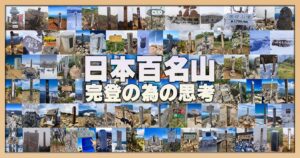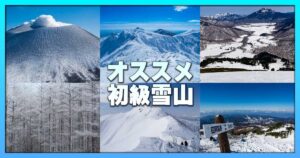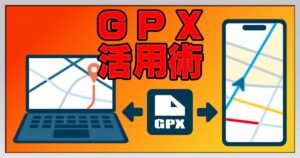「トレッキングポールを使うとどんないいことがあるいいのか?」「使う場面や使い方がいまいちわからない」「漫然と持ってる」といった方もいるのではないでしょうか?必ずしも必要な道具ではなく、筆者も使ったり使わなかったりします。また伸縮式、折り畳み式、材質もカーボンありアルミありなどのタイプもありそれぞれ特性が違います。
使う局面、逆に使わない局面、使い方、裏技的な小ネタなど、筆者のトレッキングポールの使い方のあれこれを共有したいと思います。
そもそも何のために使うのか?
体力の消耗を抑えるために使用します
もっと正確にいうと脚力の消耗を抑えたいから使います。
また、使わないという山行でも足を痛めたなどのトラブル時に使う想定で持っていく事があります。
どのように使うのか
バランスをとる
一番よく聞くワードだと思います。石や木の根の張り出し、不規則なアンジュレーションなどが多い登山道で歩く際よろめいてしまったり、足運びがしづらいといったことがあると思います。こういったストレスも積み重ねで体力を消耗します。そういった場面で、トレッキングポールを使うことにより安定感が増しストレスが軽減され体力の消耗が抑えられます。岩や木などに手を添えて歩くのと同じ効果だと思ってます。ただ、これだけの為だけに持っていてもしょっちゅうそういった場面でなければ邪魔な存在になってしまい逆にストレスになってしまいます。
腕の力を借りる
一番の使い方としてはこれだと思ってます。特に登りや平面です、腕の力を使い(体重をかけるのではない)積極的に脚力の足しにします。大げさに言うと、交互に前についたポールに対し腕の力を使いこぐような動作です。
下りも、山側に突いてう横向きで降りるといったことをして足の負担を少なくします。
筆者の場合はロングだったり久しぶりの登山の時は、二の腕や肩なんかも筋肉痛になったりします。
使わない場面・使う場面
使わない場面
説明上、先に筆者の使わない場面をお伝えします。
- 鎖場、急峻な岩場で手を使う局面
- スピードハイク、もしくは走る時
- ザックデポして寄り道するとき
特に1番目はポールが引っかかる、持ったままだと手が使いにくく、危険なことが多いので、めんどくさがらずしまいます。
使う場面
上記使わない場面以外で体力の消耗を抑えたい時です。
- テント泊装備などの荷物が重いとき
- ピッケルを使う局面以外の雪山
特に2番目の雪山は使わないとパフォーマンスが著しく落ちるぐらいです。また使わない場面以外と言いましたが、雪山は走ったり早く歩くということはしません。鎖(ロープ)などがある場合がありますがその時はしまいます。※そういったケースだとすでにピッケルに持ち替えているケースがほとんどだと思います。
トレッキングポールのタイプや材質について

筆者が現状使っているポールは、左から、軽量アルミ折りたたみ式ポール、折り畳み式カーボンポール、伸縮式カーボンポール。筆者はこれらを使い分けます。まずはタイプや材質の違いについてポイントを説明します。
材質のポイント
材質はアルミとカーボンがあります。以下はそれぞれの特徴です。
- 価格が安い
- 軽い
- カーボンに比べて剛性が無い
- 粘りがあるので完全に折れることはあまりない
- 価格が高い
- 剛性がある
- 強度以上の力が加わると折れる
収納タイプのポイント
折り畳み式と伸縮式があります。以下特徴です。
- 軽い
- 収納するときにコンパクトになる
- 収納、展開が早い
- 展開した状態でないと使えない
- 折り畳み式に比べると重い
- 一番短い状態(収納)でも少し長く、ザックに収納しても邪魔なことがある
- 収納、展開に時間がかかる
- 一番短い状態でも使える(突くことができる)

収納した状態、上から伸縮式、下2つは折り畳み式。
一番下はアルミの折り畳み式、長さ調節機能無しなので若干細くできていて一番軽いです。
その多機能のポイント
長さの調節機能があるかないか
長さの調節機能のあり無しがあります。筆者が使ってる写真一番左の軽量アルミ折りたたみ式ポールは長さ調節機能無しのポールで、後の2つは調節機能があります。
基本下記のグリップが長いタイプでは長さ調節はほぼしません。
グリップの形状

グリップの形状が長いもの(写真左から1番目と2番目)は持つ位置を変えることでポール自体の長さをある程度変えることができます。特に真ん中はかなり長いです。行動中に長さを調節するのは結構手間だったりするので、基本はグリップが長いタイプをお勧めします。
私は持っていないですが、これ以外にもアンチショック機能付き(突いた時のショックを軽減する機構がついている)やグリップ形状がT字型のものがあります。
使い分けについて
軽量アルミ折りたたみ式ポール(長さ調節機能無し)
日帰りや使わなくても保険で持っていくポールです。長さ調節機能がありませんが、グリップが手3個ぐらいの長さがあるので問題ないです。剛性はないですが日帰りでは問題ないと思います。収納状態が一番軽量コンパクトです。
折り畳み式カーボンポール(長さ調節機能有り)
テント泊たどの荷物が多い、縦走などの時に使用しています。ポイントは「カーボン」というところでアルミより剛性があり安心感が違います。一応長さ調節機能がありますが、グリップが手4個以上もあるので長さ調節機能はほぼ使わず固定で使っています。上記アルミポールを購入するまで、無雪期はこのポール1本で済ませていました。
(長さ調節機能無しのタイプに変える予定)
伸縮式カーボンポール(長さ調節機能有り)
筆者はこのタイプは雪山専用として使っています。バスケットはスノーバスケットに付け替え、ポール先端につける先ゴム(保護キャップ)も外した状態にしています。(これをいちいち付け替えるのはかなり手間です)

先端の保護キャップは外したままで雪山専用にしています。キャップしたままだと雪にささりにくく使いづらいです。またスノーバスケットに変えてます。
また、雪山では雪の深さなどに対応するために、長さを調節するケースが多いです。そのため長さ調節機能は必須だと思います。
さらに伸縮式であることもポイントで、かなり短くできるので、急斜面のトラバースとかで極端に短くして山側に突き立てるとかできます。(ピッケル出すのめんどくさい局面等)
雪山では樹林帯ではポールは使用していることがほとんどで、ピッケルに持ち替えて、ポールをザックにしまう時は、ほぼ森林限界なのでザックにつけたポールを木の枝にひっかけるケースは少ないです。
一本で済ませたいなら、雪山をやらないという前提で、折り畳み式カーボンポールでグリップが長いタイプで、長さ調節機能無しのポールをお勧めします。
トレッキングポールの小ネタ
豆知識や小ネタです。
ダクトテープを巻く

筆者は何かしらのトラブルの時に使えるように、ダクトテープをポールに巻き付けています。
例えば、テントが破けた等です。実際にザックの一部が裂けたときに使用したことがあります。
ビニールテープやガムテープでもいいかもしれませんがより強度のあるダクトテープにしています。
他人との区別
トレッキングポールは見た目が同じようなものばかりなので、間違われるケースがあります。
なので他人と区別できるように、ステッカーを貼ったり、上記のようにダクトテープなどを巻き付けたりするのがいいと思います。(筆者は上記ダクトテープをまいてるのに持っていかれそうになったので、もっと派手目なものの方がいいです)
ストラップの通し方

ストラップはてを下から通して腕にかけます。その方が力を入れやすいです。
先ゴム(保護キャップ)はなくしやすい
トレッキングポールの先についているゴム(先ゴム)は外れやすく気づいたらなくなっているので、替えを携帯するといいです。場所によっては、先ゴムがないポールの使用を禁止しているところがあります。
経験上、モンベルの先ゴムは外れにくいです。
雪山用は専用にすると便利
雪山をやるのであれば、スノーバスケット換装、先ゴムは外して専用にすると便利でおすすめです。これらをいちいち付け替えるのは非常に面倒です。
まとめ
あくまで筆者のトレッキングポールの考え方の話で、トレッキングポールの全てではないですが、筆者の使い方が皆さんのトレッキングポール選びなどの参考になれば幸いです。
トレッキングポールを選ぶときは実際ショップに行って確かめることをお勧めします。ここでは触れませんでしたが長さが自分に合ってるかどうかもチェックしてください。